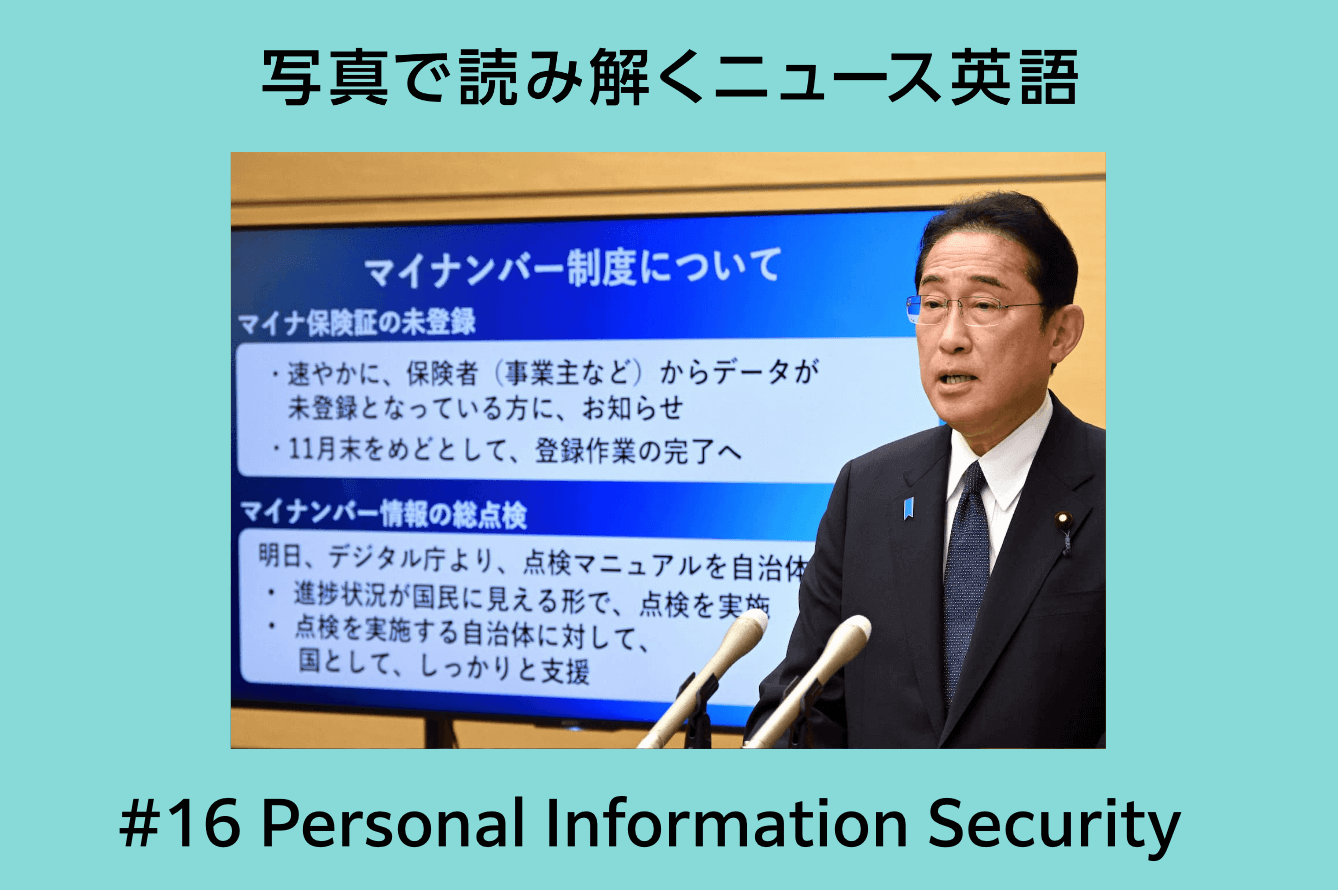写真で読み解くニュース英語 #21 Extreme Weather

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?
このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!
異常気象を阻止するためには……

突然の大雨の中、交差点を渡る人。東京都。2024年7月16日。AFP/アフロ
この夏も全国的に厳しい暑さが続きました。気象庁の統計では、最高気温が35℃以上の extremely hot day「猛暑日」の年間日数が、東京では過去20年で概ね1桁から2桁台へと増加し、昨年には22日を記録しました。また、かつては猛暑とは無縁だった札幌でも、2020年代に入って猛暑日が観測される年が続いています。近年の日本の暑さは、もはや extreme weather「異常気象」(extreme「極端な」weather「天候」)と呼んで差し支えない段階に来ています。
私たちの周りの異常気象は枚挙にいとまがありません。本州では真夏の40度近い気温も珍しくなくなり、日常的に heat stroke「熱中症」の危険性が高まっています。この夏の全国高等学校野球選手権大会(甲子園)では、もっとも気温が高い時間を避けて、試合を午前と夕方に行う「二部制」が初めて導入されました。また、いわゆる guerrilla thunderstorm「ゲリラ雷雨」(自然な英語では localized thunderstorm「局地的な雷雨」など)が頻発し、linear rainband「線状降水帯」の発生による浸水被害などが増えています。さらにアメリカ西海岸では、7月に heat dome「ヒートドーム現象」と呼ばれる異常な気温上昇が続きました。これは high-pressure system「高気圧」が特定の地域に停滞して、熱がドーム状に閉じ込められ、その地域の気温が異常に上昇する現象です。この影響で、ネバダ州のラスベガスでは最高気温が48.3℃、デスバレーでは53.3℃にも至る酷暑が到来しました。
このような異常気象の原因は何でしょうか? 直接の要因としては、pressure pattern「気圧配置」、westerlies「偏西風」、seawater temperature「海水温」などを含む偶発的な気象条件によって異常気象が発生すると説明されてきました。例えば、8月の台風5号は観測史上3例しかない東北地方の太平洋側から西に上陸する進路をたどりましたが、これは当時の偏西風や高気圧の位置によって台風が通常のように西日本側から東に進まなかったためです。また、太平洋の海水温が平年より高い状態が続く El Niño「エルニーニョ現象(もとはスペイン語で「男の子」の意味)」や、反対に低くなる La Niña「ラニーニャ現象(もとはスペイン語で「女の子」の意味)」も異常気象の要因とされています。これらの現象は数年の周期で発生し、日本の夏の気温や台風の発生に影響を与えてきました。
しかし、私たちが最も心配するべきは、異常気象と長期的な global warming「地球温暖化」との関係です。近年では、大気中の greenhouse gas「温室効果ガス」の濃度が高まるにつれて地球の平均気温が上昇し、precipitation「降雨」のパターンが変動することで異常気象の発生頻度が高まっていると考えられています。地球温暖化は年を追うごとに進行しているため、温暖化に起因する異常気象が繰り返し発生するようになれば、後戻りのできない climate change「気候変動」につながるでしょう。
ただ、地球規模の気候変動に対して実証実験を行うことは不可能であり、地球温暖化や気候変動そのものに対する skepticism「懐疑論」も今なお存在します。こういった疑念に明確な回答を与えるべく、20世紀半ば以降、さまざまな climate model「気候モデル」を用いた研究が進められてきました。この分野の第一人者であるプリンストン大学の真鍋淑郎(しゅくろう)博士は、大気と海が熱や水蒸気をやりとりする過程を計算に組み入れた「大気海洋結合モデル」を発表し、現代の気候研究の基礎を築きました。この功績を評価され、2021年には、Nobel Prize in Physics「ノーベル物理学賞」を授賞しています。現在では、真鍋博士の研究成果を基にした event attribution「イベント・アトリビューション」と呼ばれるコンピューターシミュレーションが発達し、異常気象が自然ではなく人間の活動による温室効果ガスの増加で発生しているということが観測できるようになりました。これに基づき2021年8月には、国連の Intergovernmental Panel on Climate Change「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、地球温暖化が一部の異常気象の原因であることに疑いの余地はないと結論づけています。
地球温暖化による異常気象が気候変動として常態化すれば、私たちの生活は大きな影響を受けるでしょう。中でも食糧への影響は計り知れません。近年では、海水温の上昇により fishing ground「漁場」が変化し、日本各地で伝統的な漁業が大きな試練に直面しています。また農業においても、気候の変化による品質低下や収穫量の減少が多くの作物で問題となっています。それに加えて、torrential rain「豪雨」や flood「洪水」、あるいは drought「干ばつ」による作物被害のリスクも高まっています。これは日本に限った現象ではありません。事態が改善しなければ、世界規模の food crisis「食糧危機」や famine「飢餓」につながることも懸念されています。
住環境への影響も深刻です。南太平洋の島国 Tuvalu(ツバル)では、地球温暖化による sea level rise「海面上昇」が国家存続に対する threat「脅威」となっています。同様に、世界有数の観光地であるイタリアの Venice(ヴェネツィア)も深刻な浸水被害を受けています。イタリア語で「高水」を意味する acqua alta「アクア・アルタ」の原因として、従来の地理的な要因に加えて海面上昇が指摘されています。また、東アジアにおける夏の豪雨災害も激甚化しています。
私たちは、異常気象を new norm「ニューノーマル、新常態」として受け入れるしかないのでしょうか? 人が自然に対してできることは限られていますが、国際社会も無策ではいられません。主要な温室効果ガスである carbon dioxide(CO2)「二酸化炭素」の排出を削減するために、世界的に decarbonization「脱炭素化」の取り組みが進められています。ただ、各国の意識には大きな隔たりがあることは周知の事実です。European Union「欧州連合」が牽引役となってきたものの、依然として多くの国々が石油・石炭・天然ガスなどの fossil fuel「化石燃料」に依存しています。例えば、中国は発電における化石燃料の比率を下げて自然エネルギーへの転換を進めていますが、全体の発電規模が大きいため、2023年末時点ではインドとアメリカを上回る世界最大のCO2排出国となっています。ただ、火力発電における石炭への依存度ではインドが首位となっています。
従来のエネルギー政策を転換できないという点では、日本も例外ではありません。政府のアプローチは、脱炭素化への取り組みと経済発展のバランスをとるものですが、もともとエネルギー自給率が低いところに2011年の Great East Japan Earthquake「東日本大震災」が発生し、nuclear power station「原子力発電所」の大半が現在に至るまで停止したままです。その結果、化石燃料への依存度は2022年度に83.5%に達しました(資源エネルギー庁)。しかし、この依存度を減らすために原発を restart「再稼働」することについては、安全上のリスクが伴います。また、ロシアのウクライナ侵攻を発端とするエネルギー需給のひっ迫によって、欧州を含めて原子力発電へ回帰する動きが出ていることも新たな懸念材料となっています。
気候変動による影響については、日本は変化に adaptation「適応、順応」することで被害を軽減しようと試みています。2018年12月には Climate Change Adaptation Act「気候変動適応法」が施行され、国、地方公共団体、事業者、国民、それぞれが適応の推進を担うことになりました。具体的には、高温への耐性のある農作物の開発や、治水インフラの整備などが想定されています。ただ、同法は地球規模の問題に対処するための包括的な枠組みであるため、実効性のある解決策につながるかどうかは、今後の社会の取り組み次第だと言えるでしょう。
最後に、私たち個人が地球温暖化、ひいては異常気象による影響を和らげるためにできることを考えてみましょう。power saving「節電」、public transportation「公共交通機関」の利用、reduce waste「ごみを削減する」、reduce food waste「食品廃棄物を削減する」、などはすでに知られていますが、digital carbon footprint「デジタル・カーボン・フットプリント」という概念はまだまだ浸透していません。これは、デジタル機器、ネットワーク、ストリーミングサービスなどの使用によるCO2の排出量を可視化するものです。例えば、Plan Be Eco 社の試算によると、動画投稿サービスTikTokのデジタル・カーボン・フットプリントの排出量は、CO2 換算で毎分 2.63 グラムになるそうです。 TikTokの2023年の月間アクティブユーザー数は15億人に上るため、総計では莫大な排出量になることがわかります。世の中の DX (digital transformation)「デジタル・トランスフォーメーション」が進む中で、紙などの目に見える物質を消費しなければ資源の節約になると考える人は多いかもしれません。しかし、一見実体がないように見えるデータにも、その裏に消費されている膨大なエネルギーがあるのです。電子機器を使うときにも、私たちはそのことに思いを馳せる必要があると考えます。
著者の紹介
内藤陽介
翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長
京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。