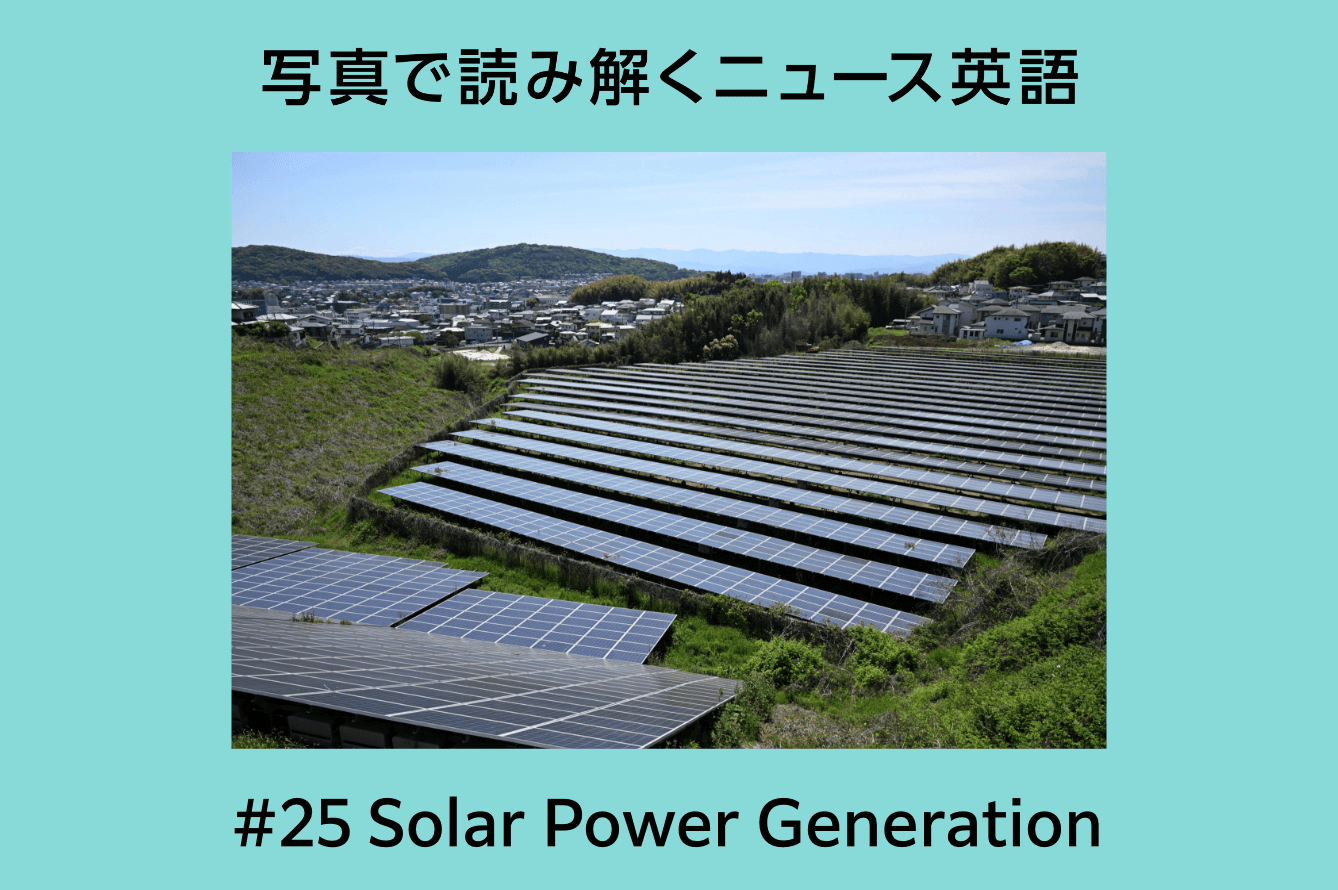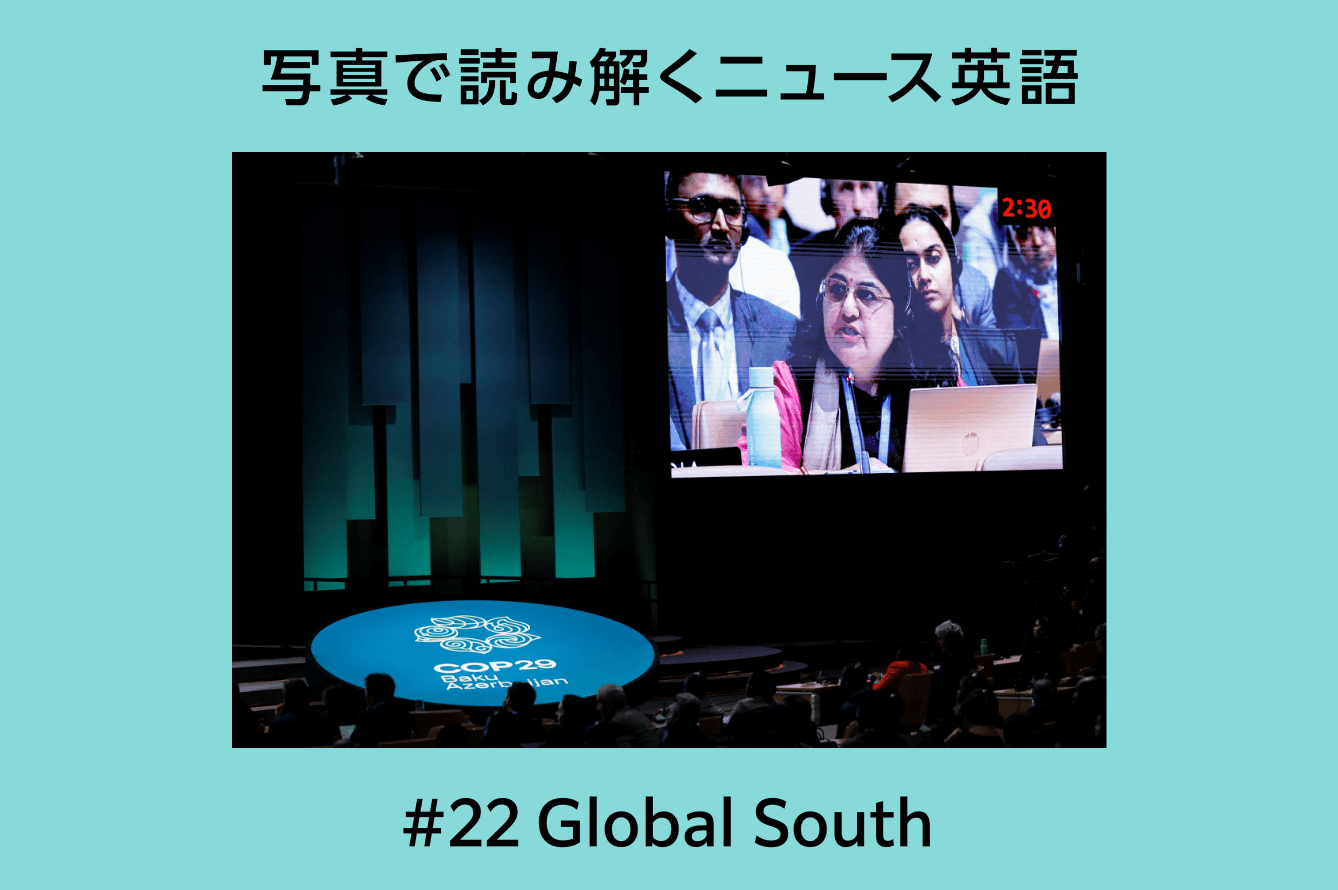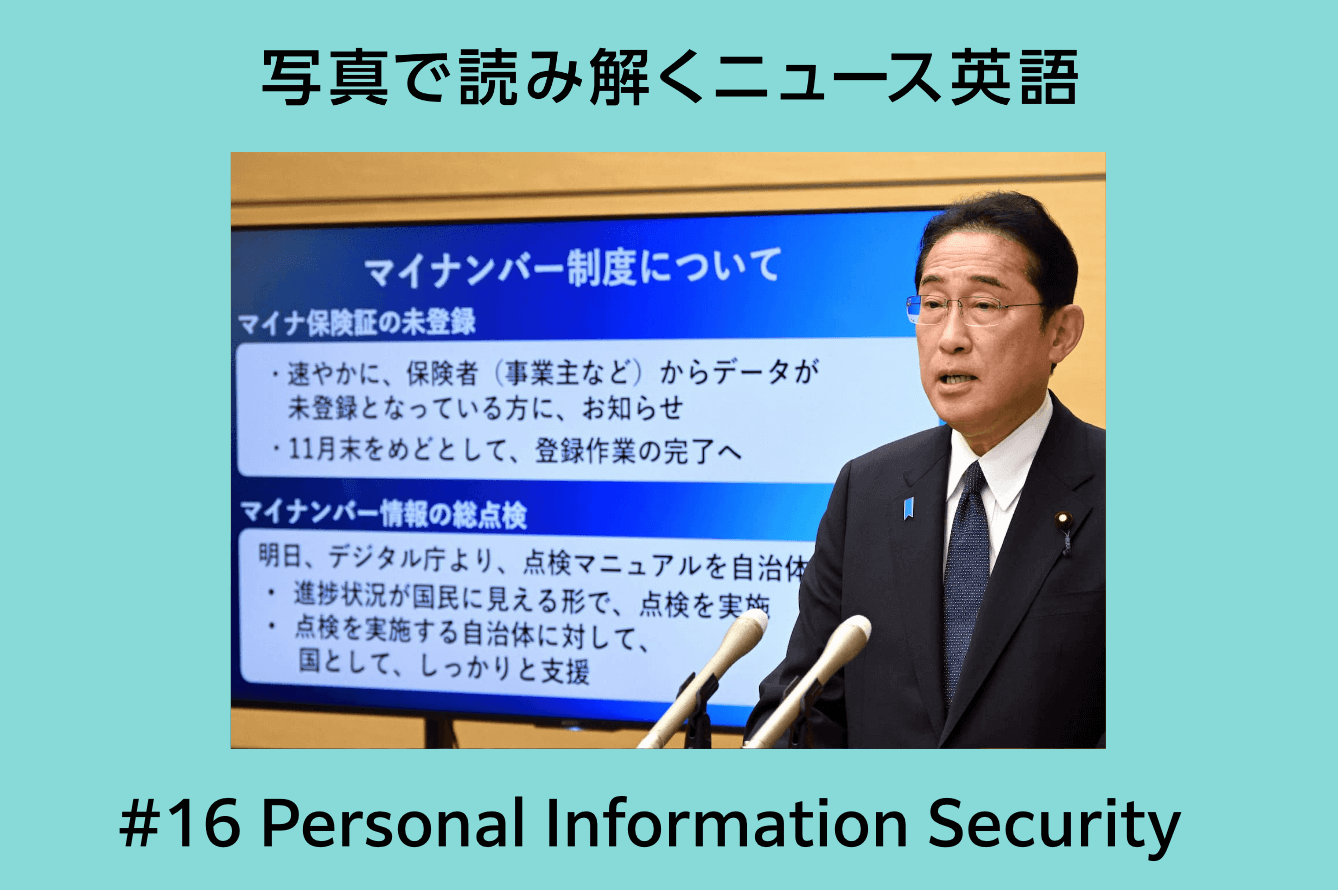写真で読み解くニュース英語 #28 Human-Bear Conflict

世界中で報道されるニュースを、英語で読んでみたくありませんか?
このコラムでは、旬なニュースを写真で紹介し、そのテーマについて解説しながら、英語でニュースを読む手助けになるように関連する単語や表現を取り上げます。環境問題やジェンダー平等など、世界中が抱える課題に触れながら、英語学習にお役立てください!
長期的な管理体制を見据えてできることとは?

果樹園近くの遊歩道の入り口に、クマ注意の標識が設置されている。岐阜県飛騨市。2025年11月14日。ロイター / アフロ
2025年秋、日本の自然は人間に対して大きな牙をむきました。北海道から中部地方にかけての山間部を中心に、wild bear「野生のクマ」が人里に頻繁に出没するようになり、遭遇した住民を attack「襲撃する」事案が相次ぎました。クマの多くは住宅地や市街地でも目撃されています。環境省の2025年度の統計によれば、こうした Human-Bear Conflict (HBC)「人とクマの軋轢」による人身被害者数は、4月~11月の8カ月間で230人に達し、13人が死亡しました(昨年度は1年間で被害者85人、死亡3人)。中でも、秋田県では最多となる66人が負傷、4名が死亡したということです。
この異常事態に対して、世論は animal protection「動物愛護」と human life「人命」で対立しています。クマの culling「駆除」が報じられるたびに、抗議の電話が自治体に寄せられるそうです。これに対して、駆除に反対するなら彼らがクマを引き取るべきだ、などの皮肉を込めた反論も見られます。この点について、筆者はクマの問題は単純な二元論で片付けられるものではないと考えます。人命が top priority「最優先事項」であることは大前提であり、クマが頻繁に出没するようになった時点で、人の手によるクマの管理は失敗したと考えるべきでしょう。私たちは対立を煽るのではなく、原因の検証と今後の対策を中心に、管理体制の改善を図る必要があります。
2025年にクマの出没が増加した原因について、興味深い研究結果が公表されています。すでに知られているメカニズムとしては、年によって beechnut「ブナの実」などの acorn「ドングリ」の結実不良がクマの食糧の減少を引き起こし、行動圏が人里へと拡大してきたことが挙げられます。さらに、秋田県の林業研究研修センターの最新の調査によれば、ブナの実の rich harvest「豊作」と poor harvest「凶作」の周期が、2021年以降は従来よりも短い1年ごとに繰り返しているとのことです。センターは、2025年が凶作だったことがクマ出没増加の一因としていますが、これに加えて、餌が豊作だった2024年に母グマの出産が増え、今年はクマの population「個体数」そのものが増加している可能性があるとのことです。
また、warm winter「暖冬」の年にはクマの hibernation「冬眠」が遅れ、出没期間が延びているとの報告もあります。北里大学獣医学部の研究グループは、2025年1月に真冬の青森県の八甲田山系でクマが歩く様子を撮影しました。雪深い時期に歩行する様子が記録されたのは初めてだったとのことです。研究グループは、冬眠期間中に den「巣穴」を移動する個体もいる一方で、冬眠期間そのものが短くなっている可能性もあると指摘しています。冬になったからといってクマが出ないとは限らないことから、近隣住民にとってはこれからも安心できない日々が続きます。
これらの現象の背景にある大きな要因として、global warming「地球温暖化」や climate change「気候変動」を連想する方も多いはずです。クマの出没との直接的な因果関係は明らかではありませんが、世界各地で発生している気候や生態系の変化を考えれば、十分にあり得ることだと思います。より直接的な要因では、地方の depopulation「過疎化」や里山*の利用の低下で、人とクマの間に存在した buffer zone「緩衝帯」が機能しなくなったことなどが挙げられます。こうした構造的な問題は、今後さらに悪化していくでしょう。クマの問題は人間にとって長い時間をかけて積み重なっていくリスクだと考える必要があります。
ところが、日本の現行制度には問題が山積しています。クマの捕獲や駆除については、地域の hunters’ association「猟友会」に要請することが大半で、彼らのボランティア的な活動に依存しているのが現状です。これらの団体は行政機関の permanent organization「常設組織」ではないため、クマの出没や襲撃があってからの事後対応になりがちです。また、ハンターの高齢化によって hunting license holder「狩猟免許保有者」が減少する一方で、日当数千円程度と言われる報酬の低さが後継者不足を深刻化させています。危機が長期化するほど制度疲労が露呈してしまう現状では、日常的なクマの管理体制の構築には多くの課題が立ちはだかります。
海外の human-bear conflict はどのように対処されているのでしょうか? 米国モンタナ州では、人間と grizzly bear「グリズリーベア(ハイイログマ)」との coexistence「共生」が課題となっており、行政は有事の対応を減らすために日常の管理体制を強化しています。中心となるのは、住民の awareness-raising「意識啓発」と cooperation「協力」です。ゴミ・家畜飼料・果樹などの attractant「誘引物」の管理を徹底し、集落周辺の樹木の伐採や electric fence「電気柵」の設置によって緩衝帯を維持し、クマとの衝突を避ける取り組みを進めています。また、出没や襲撃の事案を原因別に整理・公開して、誘因管理や予防対策をさらに進めています。一方、行政の常設チームがクマの行動を継続的にモニタリングし、計画的な捕獲を実施しています。長期的な取り組みとしては、周辺の habitat「生息地」や森林の餌環境を整え、気候変動などの変化も追跡しています。
日本にとって、モンタナ州の取り組みは大いに参考になるでしょう。クマが「出てきてから対処する」だけでなく、住民が日常的に誘因を管理し、詳細な分析情報を共有することで、被害の芽を早い段階で摘みとることができるはずです。そのためには、常設の専門職や現場で対応する人材を civil service「公務」に近い形で位置づけ、安定的に確保すること、危険を伴う現場対応に見合う compensation「報酬」の設定、equipment「装備」の供給、training「訓練」の実施などを制度として整えることが求められます。また、警察・自治体・専門家・猟友会の coordination「連携」を迅速に行えるように、標準的な protocol「手順」を準備しておくことも欠かせません。
もっとも、日本でもクマ対策の平時の取り組みは進みつつあります。住民啓発の観点から、山形県は米沢市と鶴岡市に pilot area「モデル地区、実証実験エリア」を設置し、そこで住民と専門家がクマについて共に学び、対策を点検し、誘因を減らす取り組みを進めています。また、北海道の島牧村は総延長約18kmの電気柵を設置し、住民が日常的に brush clearing「草木の伐採・除去」を実施することによって、7年前には年間100件以上あったクマの目撃が2024年には約20件まで減少したと報じられています。
冬眠入りの遅れや冬でも活動する個体が増え、クマの出没は seasonal phenomenon「季節性の現象」ではなくなりつつあります。餌環境や気候の変化、里山の荒廃などが進めば、今回の問題は temporary problem「一過性の問題」ではなく、長期的なリスク課題として続く可能性が高いでしょう。感情的な対立に流されず、クマの誘因削減や個体管理を平時から積み重ねる preventive management「予防管理」を社会の標準にしていくことが、人命第一とクマの生態系の維持を両立させる現実的な道筋だと考えます。
* 里山:国際的な自然環境保護の分野で、日本の事例として satoyama という用語が使われることがあるが、一般的な英語では human-managed buffer zone between settlements and surrounding nature「集落と周囲の自然の間にある、人によって管理された緩衝地帯」のように説明するとわかりやすい。
著者の紹介
内藤陽介
翻訳者・英字紙The Japan Times元報道部長
京都大学法学部、大阪外国語大学(現・大阪大学)英語学科卒。外大時代に米国ウィスコンシン州立大に留学。ジャパンタイムズ記者として環境省・日銀・財務省・外務省・官邸などを担当後、ニュースデスクに。英文ニュースの経験は20年を超える。現在は翻訳を中心に、NHK英語語学番組のコンテンツ制作や他のメディアに執筆も行う。