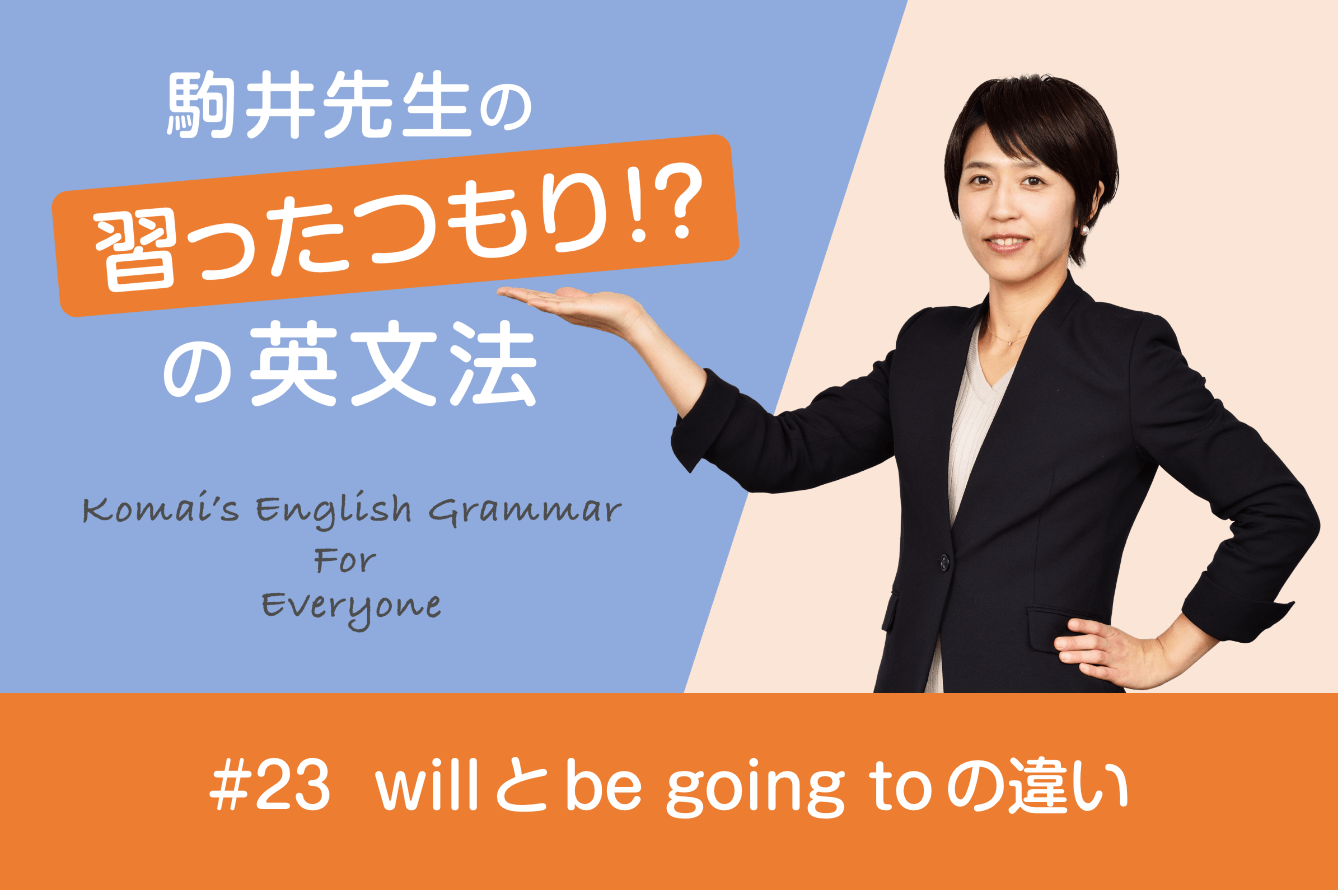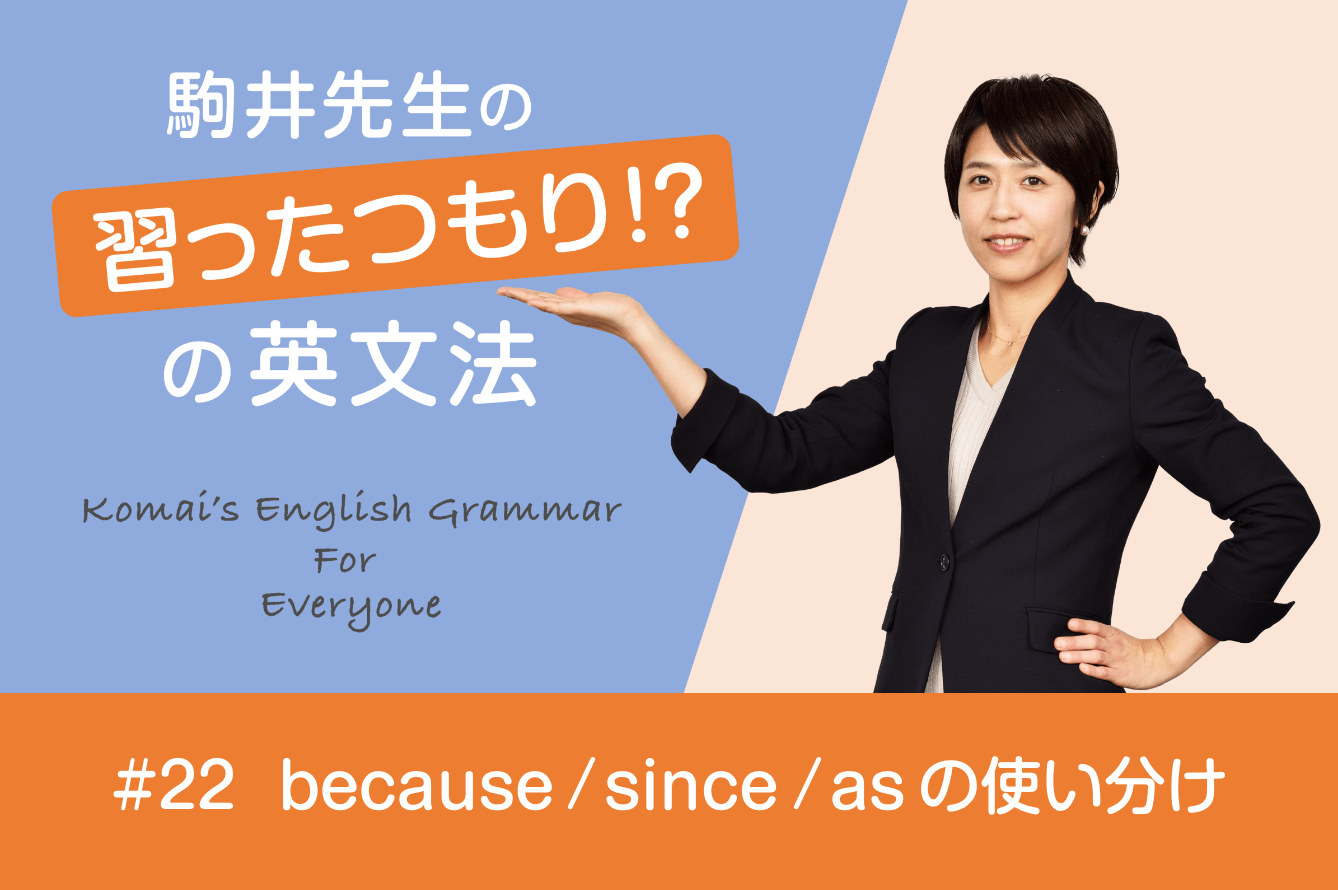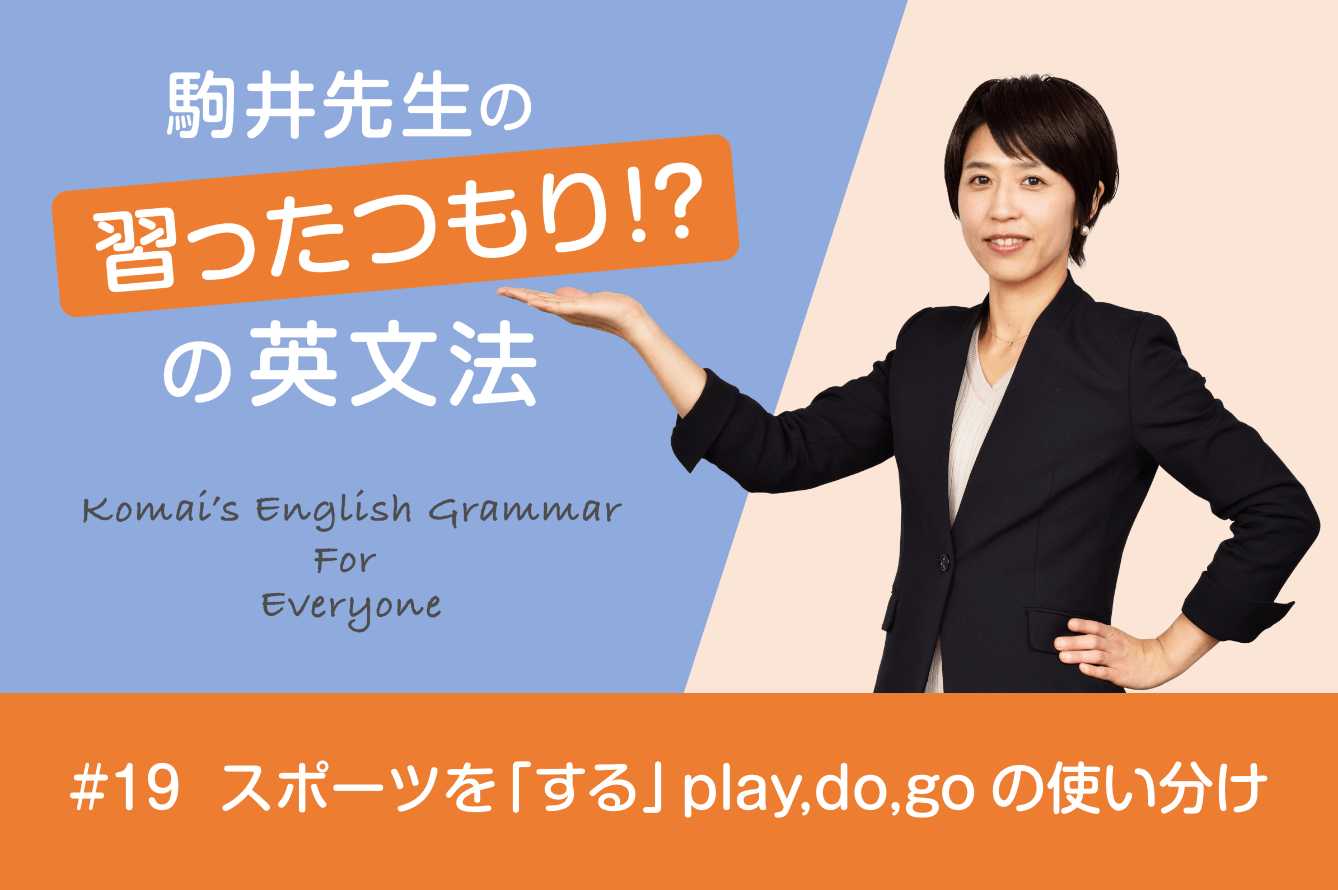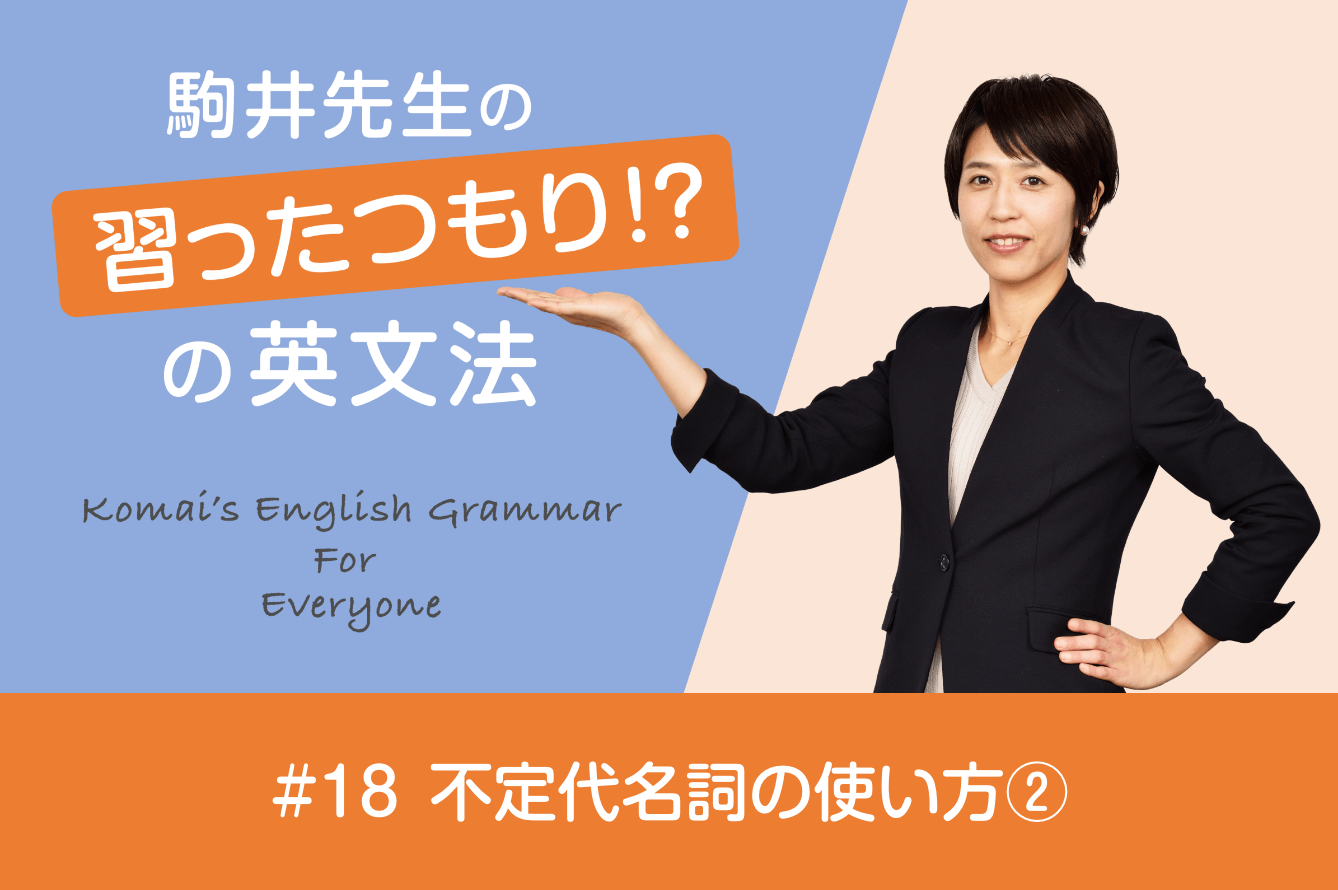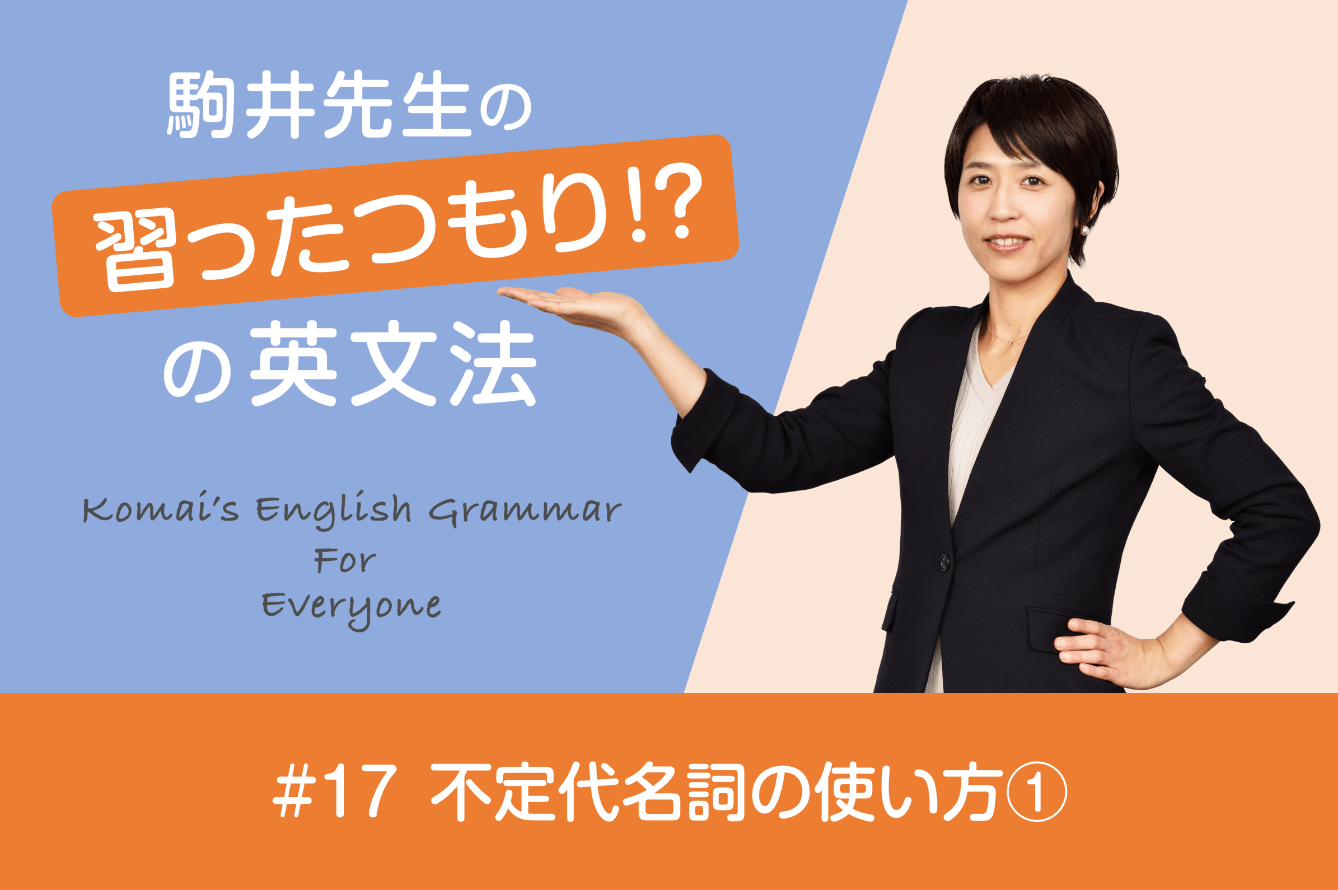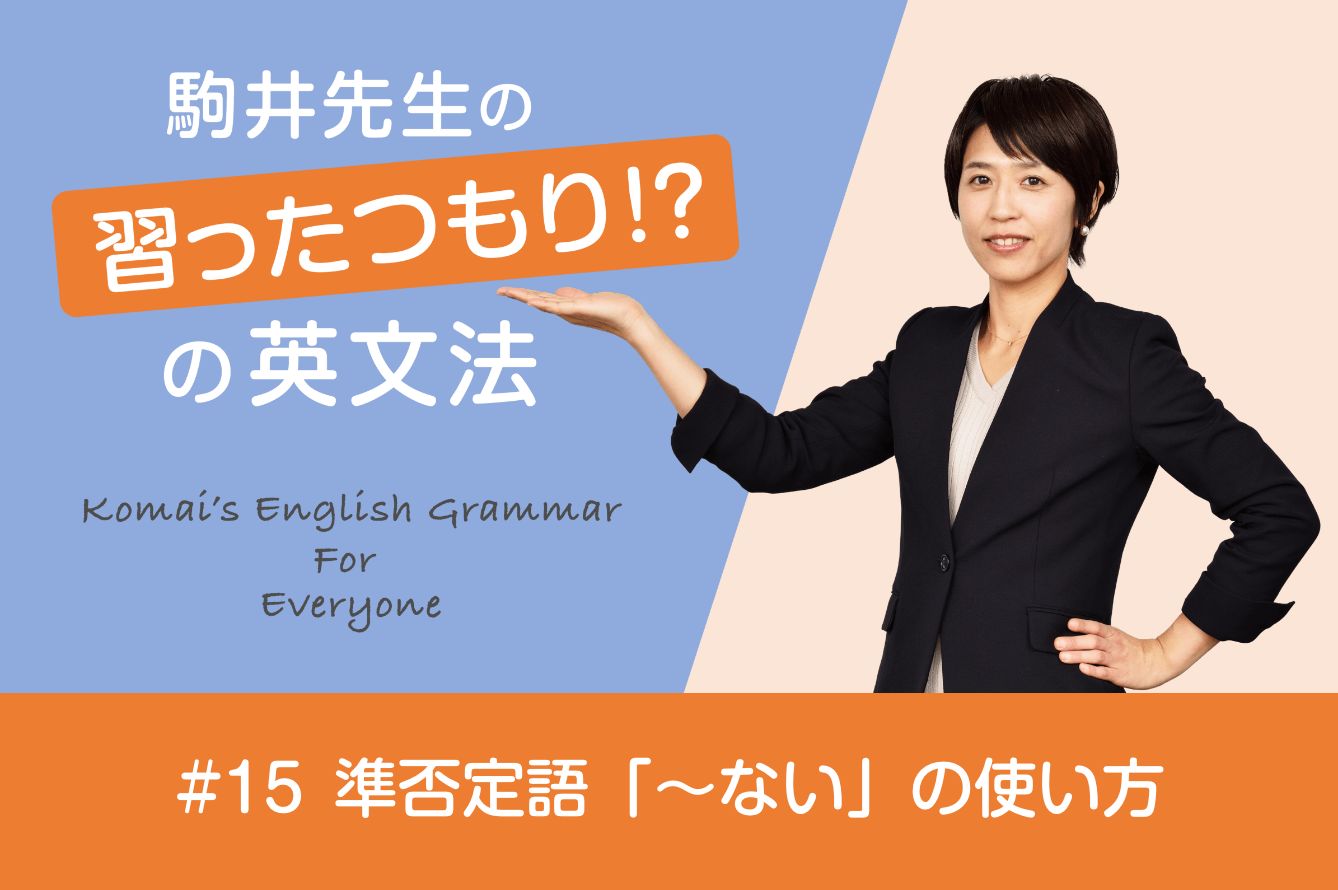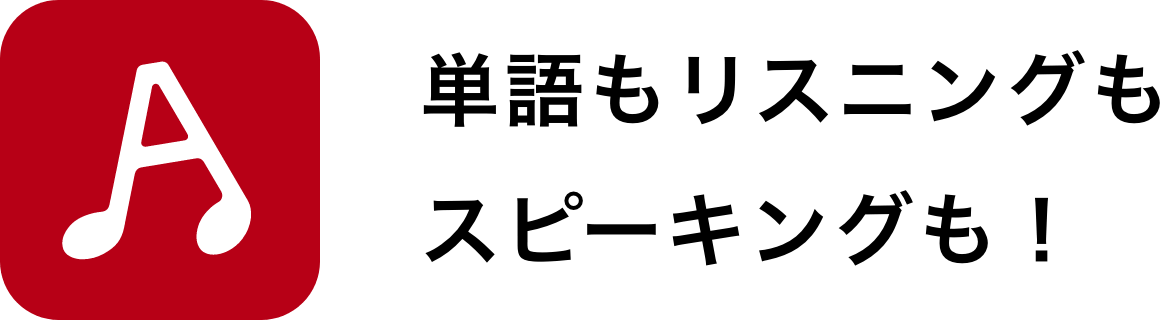駒井先生の習ったつもり!? の英文法 #24 形式主語・形式目的語 it を使いこなそう
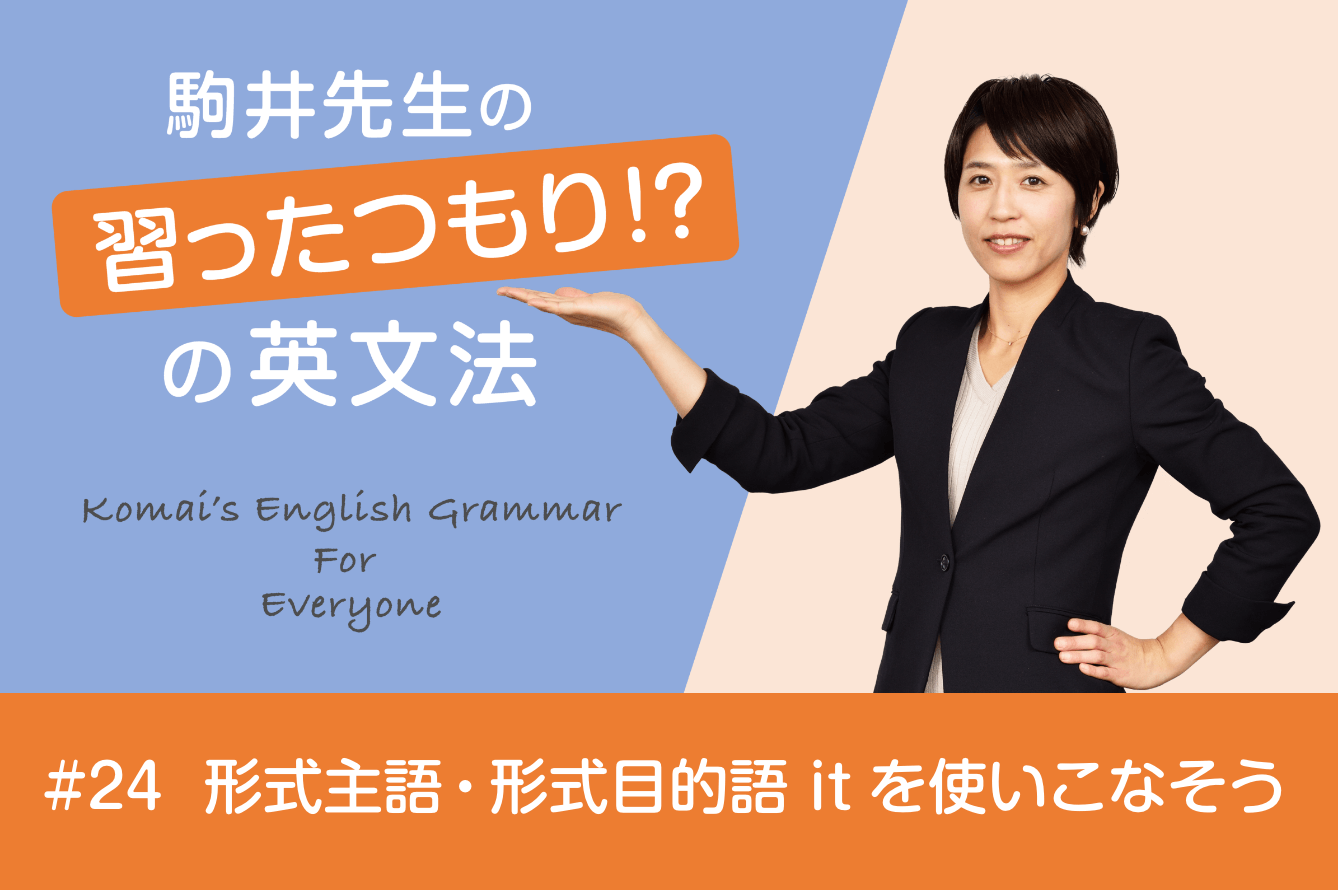
学校で習ったはずの英文法。日常会話にもよく出てくる使い方なのに、すっかり忘れていませんか? 身近にあるのに意外と知らない「習ったつもり」の英文法を、大学や専門学校、企業で教鞭をとるTOEIC人気講師・駒井亜紀子先生が解説してくれるコラムです。
長すぎる主語・目的語に代わる、とりあえずの it
みなさん、こんにちは。駒井亜紀子です。
突然ですが、みなさんに問題です!
(このコラムでは最初から問題を出すことがよくありますので心のご準備を)
次の英文の it は何を指していますか。
・ I bought a new microwave oven, but it was damaged.
この英文は「私は新しい電子レンジを買いましたが、それは壊れていました」という意味で、it は a new microwave oven(新しい電子レンジ)を指します。
it は、基本的には前述された名詞を指して「それ」と訳し、その名詞の代わりをする単語です。
文字通り、「名詞の代わりをする品詞」なので、「代名詞」と呼ばれます。
では、次の2つの英文にある it は何を表しているかわかりますか。
・ It is said that the temple was built more than 20 years ago.
・ Tom made it possible to solve the problem.
さて、今回は、この代名詞 it の特別な使い方を2つ学んでいきましょう。
答えはこのコラムの中で紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください!
1. 形式主語の it
代名詞 it には、「前述された名詞の代わりをする」という基本的な役割があると言いましたが、上記の2つの例文では違う役割をしています。
まずは、もう一度2番目の例文を見てみましょう。
It is said that the temple was built more than 20 years ago.
主語に代名詞 it が置かれていますが、その前に名詞は見当たりませんね。
では、この it は、いったい何を表しているのか……
実は、この it は「that 以下の内容の代わりに置かれた主語」の役割をしています。
と言うと、「意味がわからない……」と、ほとんどの方が強い絶望を感じることは理解しています。
大丈夫です。安心してください!
みなさんに寄り添いながら少しずつ解説していきます!
この文の日本語訳を確認してみましょう。
It is said that the temple was built more than 20 years ago.
(その寺は20年以上前に建てられたと言われています。)
英文と日本語訳を見て、何か気づいたことはありますか。
もし、みなさんが、主語にある it が「それは」とは訳されていない点に気づいたのなら、鋭い視点をお持ちです!(先ほど絶望した人を救う言葉)
英文の主語 it は「それは」と訳されておらず、日本語訳の主語は「その寺は、20年以上前に建てられた(the temple was built more than 20 years ago)」になっていますよね。
そうです、この文の本当の主語は、that 以下に書かれている内容です。
つまり、it はとりあえず置かれた主語であり、it 自体に意味はありません。とりあえず、本当の主語が長いから、その代わりに置かれた it なのです。
くどいようですが、この文の本当の主語は「その寺は、20年以上前に建てられた(the temple was built more than 20 years ago)」です。
この that 以下の部分を「真主語」と呼び、一方で、it は単に形式的に置かれた主語なので「形式主語」あるいは「仮主語」と呼びます。
少し絶望の淵から這い上がってこれましたか。
では、いくつか例文を見て、日本語に訳してみましょう。
1)It is believed that he is the most talented musician.
まず、「真主語」はどれかを確認しましょう。
it は「形式主語」で、「真主語」は that 以下の he is the most talented musician(彼は最も才能のあるミュージシャンだ)の部分ですね。では、「真主語」を主語として一文を訳してみましょう。
日本語訳は「彼は最も才能のあるミュージシャンだと信じられています」となります。
次の例文を見てみましょう。
2)It is a pity that you missed the last train.
さて、これは訳せますか。a pity は「残念なこと」という意味です。
「形式主語」の it が置かれ、「真主語」は that 以下です。
しっかり、「真主語」を主語に当てはめて訳してみましょう!
日本語訳は「あなたが終電を逃したなんて残念ですね」となります。
少しわかりやすいように意訳していますが、直訳すると「あなたが終電を逃したのは残念だ」となります。
もう一つ見てみましょう。
3)It doesn’t matter whether he agrees or not.
少し難しくなりましたね。ここでも「形式主語」の It が使われています。
まず前半と後半で、2つの大きなブロックにして考えてみましょう。
It doesn’t matter… は「重要ではありません」という意味。
後ろの whether he agrees or not は「彼が賛成しようとそうでなかろうと」という意味です。
「真主語」は whether 以下の部分なので、そこを主語とすると、
「彼が賛成しようとそうでなかろうと、重要ではありません」となります。
例文の2番と3番はこの形のまま日常会話でも頻繁に用いられ、使い勝手がいい文です。
ぜひ「定型文」のように覚えておきましょう!
- It is a pity that S+V… : ~とは残念だ
- It doesn’t matter whether S+V… : ~かどうかは重要ではない
いかがでしたか。
it は「形式主語」であることを認識し、かつ、正しい「真主語」を見抜いて正しく訳すことができましたか。
ちなみに、最初の
It is said that the temple was built more than 20 years ago.
の文や
1)It is believed that he is the most talented musician.
の例については、以下のような考え方も押さえておきたいところです。
これらの文は、It is said that…、It is believed that… と、受動態になっていますね。
これらの文を能動態で表す場合、「一般論として、人々が that 以下の内容を話している(信じている)」というニュアンスとなるため、主語に People[They] を置き、
People[They] say that the temple was built more than 20 years ago.
People[They] believe that he is the most talented musician.
という書き方になります。
それを受動態にする際に、本来なら目的語の that 以下が主語になりますが、それだとあまりに主語が長くなりすぎるため、代わりに it を主語にしたのです。
また、「形式主語」については、コラム第2回(It takes… での説明)と第4回でも触れています。違う構文で形式主語の it を使っているので、ぜひこちらも確認しておきましょう!
2. 形式目的語の it
次にこちらの例文をもう一度見てみましょう。
Tom made it possible to solve the problem.
「形式主語」の it を学ぶと、この it の役割も、なんとなく察しがつく人がいるかもしれません。
そういう方は鋭い洞察力をお持ちです!(絶望から救う言葉2回目)
こちらの it は made(make の過去形)の目的語になっています。
it を説明する前に、一度、動詞 make の使い方を整理しておきましょう。
動詞 make には以下のような用法があります。
- <make+O(目的語)+C(形容詞)>:OをCにする
it は目的語の役割を果たしていますね。例文には Tom made it possible… とあるので、そのまま訳すと「トムはそれを可能にしました」という意味になりそうですが…そのようには訳しません。
正しい日本語訳を見てみましょう。
Tom made it possible to solve the problem.
(トムは問題を解決することを可能にしました。
「トムのおかげで問題を解決できました」と訳すと自然な日本語になります。)
ここでもやはり、it は「それ」とは訳されていないことがわかりますね!
そう、この it も形式主語と同じように、とりあえず置かれた目的語なんです。単に本当の目的語が長いから、形式的に置かれた it です。そのため、「形式目的語」あるいは「仮目的語」と呼ばれています。
では、本当の目的語である「真目的語」はどの部分かと言うと、to solve the problem という to 不定詞の部分です。
it の部分にこの「真目的語」を当てはめて訳すのが正しい訳し方です。
形式目的語の it は上記のように、SVOC の構文の O(目的語)に置いて使う場合が多々あります。
なぜなら、SVOC の文で、O(目的語)の部分に長い句や節を用いると文の構造がわかりにくくなってしまうからです。
だから、目的語の位置に it を形式的に置くんですね。
他にも例を見ておきましょう。
下線部分が「真目的語」の役割をしています。
「真目的語」の部分には、to 不定詞だけではなく、that 節や動名詞を置くこともできます。
● consider it 形容詞 : ~だと思う
I consider it important to prepare in advance.
(事前に準備するのは大事だと思います。)
● feel it 形容詞:~だと感じる
I feel it strange that she didn’t come.
(彼女が来なかったのは変に感じます。)
● find it 形容詞:~だとわかる / ~だと思う
I found it difficult concentrating on my work at night.
(夜は仕事に集中するのは難しいとわかりました。)
このように、代名詞 it は「形式主語」や「形式目的語」として働きます。
主語や目的語が長いと、相手が何を言いたいのか理解しづらくなりますよね!
その理解のしづらさを避けるために、「とりあえず it を置く」という手段を使って、手っ取り早く提示し、具体的な内容をあとに置いています。
英語という言語は基本的に「軽い情報(わかりやすい情報)」から先に相手に渡します。具体化した内容は情報量が多くなり、相手にとって負担になります。
第22回のコラムでも「新情報は後ろに置くという構造が一般的」と書きましたが、これも、相手の情報処理の負担を軽くするという理由でしたね。
「形式的な主語・形式的な目的語」という存在に慣れないうちは使いこなすのも難しいと思いますが、まずは、上記の例文を覚えて使うことから始めてみましょう!
I hope you found it helpful to read this column!
(みなさんがこのコラムを読むことは役に立つと思ってくださっていることを願っています!)
See you next time!
(ではまた!)

TOEIC 990点(満点)、英検1級。神田外語学院、共立女子大学講師。大手企業でもTOEICの指導にあたる。外資系企業勤務を経て、英語講師へと転身。著書に『TOEIC(R) L&Rテスト はじめて受験のパスポート』(旺文社)、『TOEIC L&R TEST 200問音読特急 瞬発力をつける』(朝日新聞出版)、『駒井のたった5時間で TOEIC L&R TEST 攻略 730点』(Gakken)などがある。