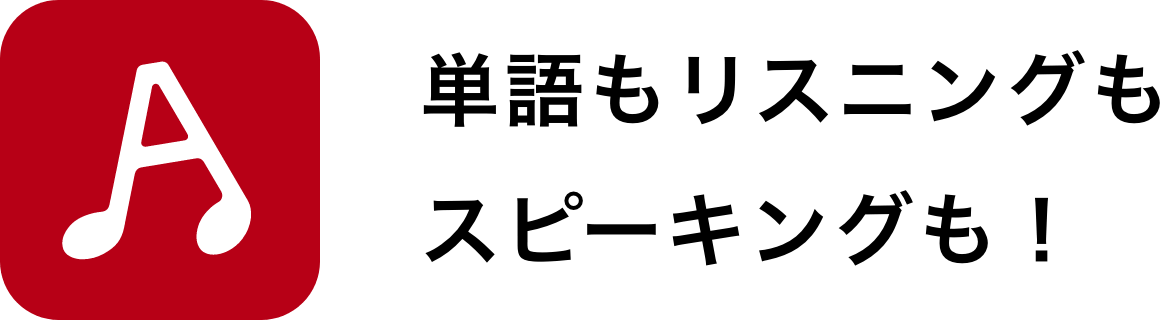生まれたばかりの英語たち #3 Civic Pride

時代とともに新しく生まれ、変化していく「言葉」。グローバル言語として使われる英語には、日本ではまだまだ認識されていない言葉があります。その誕生には、どんな社会的・文化的背景があるのでしょうか。キニマンス塚本ニキさんに「生まれたばかりの英語」について解説いただき、一緒に「新しい概念」について考えてみましょう!
Civic Pride(自分の街に対する市民の誇り)
●シビックプライド、新しそうで実は古い言葉
突然ですが、あなたは自分の町・地域に『誇り』を感じていますか? 日本語ではあまり日常的ではない「誇り」という言葉に、すぐピンとくる方は多くないかもしれませんが、今回は「都市に対する市民の誇り」を意味する Civic Pride(シビックプライド)という英語をご紹介します。
日本語にも『地元愛』や『まち自慢』など、一見似たような言葉はありますが、シビックプライドには「まちづくりに参加する市民の主体性」という意味が込められています。
実を言うとこの言葉、「生まれたばかり」の英語ではなく、産業革命の真っ只中だった19世紀のイギリスで誕生した概念です。コラムのタイトルとズレちゃってない? とツッコまれそうですが、ここ数年でヨーロッパをはじめとする英語圏で再注目されている、日本でも最近少しずつ研究や実践を通して政治やまちづくりの観点から注目を集めている言葉なので、ぜひ一緒に考えてみてほしいです!
都市部を中心に工業化が猛スピードで進んでいた産業革命時代のイギリスでは、農村部から都市部へと大規模な人口移動が起こり、これと同時に社会のあり方と「市民」という存在に対する考え方が少しずつ変わり始めていました。富裕層など民間の出資によって建設された立派な公共建物は街のシンボルとして愛され、そこで暮らすことにアイデンティティや誇りを持つ姿勢が市民の間で醸成されていきました。
19世紀後半には労働組合運動が合法化され、女性の参政権をめぐる議論も始まるなど、暮らしや政治の改善を求めて市民が政府や雇用主に訴えかける運動が盛んになり始めました。急速な都市化と共に変容する当時のイギリス社会の市民運動が、「自分たちがこの街を育てる」という主体的な意識を力づけたのかもしれません。
さらに世界初のリーグ戦であるイングリッシュ・フットボールリーグが設立され、各地域の代表フットボールクラブを応援するカルチャーが生まれたのもこの時期です。熱烈なサポーター同士の間で巻き起こる乱闘騒ぎ(hooliganism)も当時の報道に記録されていますが、どんな形にせよ、近代のイギリスでは地域の一員としての誇りが市民の間で構築されていたことがうかがえます。
あれから100年以上の年月を経て、今、アメリカやイギリス、日本を含む各国でシビックプライドの研究や実践が改めて注目されています。市民農園やゴミ拾いなどのボランティア活動から、市民と行政が対話を重ねてまちづくりを図るタウンミーティングなど、シビックプライドを向上させる方法は様々ですが、その効果と持続性はまだ試行錯誤が続いているようです。
実は、世界的に有名なロゴブランドの「I♡NY」のデザインもシビックプライドを活性化させた例だというのはご存じでしょうか? 大都市ニューヨークへの愛着を表現するこのロゴが発案された1977年当時、金融危機に次ぐ不況により治安が悪化し、街は大荒れ状態でした。生粋のニューヨーカーでグラフィックデザイナーのミルトン・グレイザーが「愛する街を見捨てたくない」という気持ちを込めたシンプルでアイコニックなデザインは瞬く間にヒットし、CMキャンペーンの影響などもあって、ニューヨークは「廃れた危険な街」から「刺激的な観光名所」に生まれ変わったのです。
それから数十年後の2001年、同時多発テロの直後、グレイザーが新しく制作した「I♡NY MORE THAN EVER」(これまで以上にニューヨークを愛している)ポスターは、オリジナルのロゴと共にシビックプライドのシンボルとして街中に出現しました。
さらにその翌年の2002年に公開されたサム・ライミ監督映画『スパイダーマン』のクライマックスで、絶体絶命の窮地に追いやられたスパイダーマンが一般市民たちの団結によって救われるシーンがあります。“You mess with Spidey, you mess with New York!”(スパイダーマンに手を出せば、ニューヨーク全体を敵に回すってことだぞ!)、そして “You mess with one of us, you mess with all of us!”(俺たちの身内にケンカを売るなら、俺たち全員が相手になるからな)という名もなき市民のセリフが出た瞬間、ニューヨークの映画館の客席から毎回大きな歓声が上がったと言われています。こんなふうにポップカルチャーを通してシビックプライドが刺激され、共有される瞬間は他にもたくさんありそうですね!
●私の住むまちのシビックプライドは?
ところで、私が暮らす東京のシビックプライドはどうなっているんだろう? と気になり、調べてみたところ、2023年に世界10都市を対象にしたシビックプライド調査を見つけました。しかし蓋を開けてみるとビックリ。「この街に愛着を持っている」「この街のあり方に共感している」「この街に誇りを持っている」などの質問をヨーロッパ、アメリカ、アジアにおける主要10都市に居住する市民に回答させたところ、大阪が9位、東京が10位と、日本の二大都市は最下位にランクインしていたのです。
東京で生まれ、幼少期を過ごしてから海外に移住し、成人後にまた戻ってきた私ですが、どうして東京で暮らしているのかと自問自答すると「フリーランスとして人脈を増やすチャンスが地方よりも多いし、商業的にも文化的にも多様な選択肢にいつでもアクセスできる。公共交通もインフラも発展しているからとにかく便利だし。でも、愛着があるかと聞かれたら…正直なんとも言えないなぁ」というのが本音なのです。
周りを見渡しても、世界トップレベルの知名度と経済力を持ち合わせ、カルチャー面でも絶大な引力を持つ街として世界中から知られてきたにも関わらず、「I♡TOKYO」に相当する街への愛着やプライドが表現された例をあまり見たことがない気がします。もちろん、マーケティング戦略的な商標ブランドの有無だけで市民の愛着は評価できませんが、東京都が18歳から39歳を対象にとったアンケートでは、「東京が好きですか?」の問いに最も多かったのは48.7%の「どちらかといえば好き」という、な〜んとも生ぬるい回答だったのです。
しかし興味深いことに、シビックプライドを育むために必ずしも自分の街が完璧な場所だと感じたり、街を大好きだと思ったりする必要はない、と研究者は語っています。先述のシビックプライド調査でも、上位にランクインした都市(トップ5は上海、バルセロナ、ロンドン、ローマ、ニューヨーク)の住民にとって、誇れるポイントはそれぞれ違うようです。結局のところ、シビックプライドの育み方や感じ方は一辺倒ではなく、その街の文化や地域性に基づいているようです。
思春期をニュージーランドで過ごし、人生の半分以上を東京で過ごしてきた私がイメージするシビックプライドには、煌びやかな商業施設や、経済活動が24時間可能な利便性よりも、安心できる隣人との交流や、そこを自分の居場所と感じられる帰属意識(a sense of belonging)が欠かせません。町や地域の魅力というものは自然発生するものでも、誰かに作ってもらうものでもなく、そこで暮らす人々が自ら生み出せるものであるような気がします。
あなたの地域のシビックプライドはいかがでしょうか? 「あまり強く感じていないかも」と思ったなら、身近なところから少しでも考えてみるきっかけになれば嬉しいです。

通訳・翻訳家・ラジオパーソナリティ
1985年東京都生まれ。9歳から23歳までニュージーランドで暮らし、オークランド大学で社会学・ジェンダー学・映像学などを学ぶ。日本に帰国後、フリーの通訳・翻訳者として国内外の社会課題の啓発や対話の現場に携わる。TBSラジオ「アシタノカレッジ」、「荻上チキ・Session」、YouTubeチャンネル「ポリタスTV」などにレギュラー出演。著書に『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(Gakken)がある。