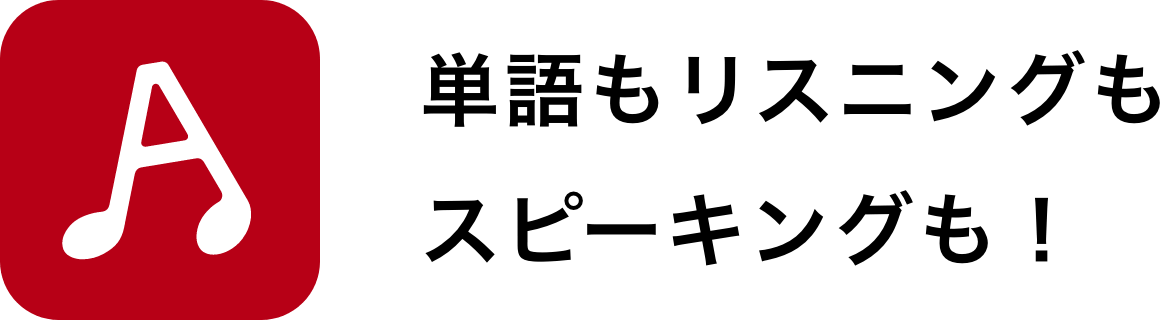生まれたばかりの英語たち #2 touch grass

時代とともに新しく生まれ、変化していく「言葉」。グローバル言語として使われる英語には、日本ではまだまだ認識されていない言葉があります。その誕生には、どんな社会的・文化的背景があるのでしょうか。キニマンス塚本ニキさんに「生まれたばかりの英語」について解説いただき、一緒に「新しい概念」について考えてみましょう!
touch grass(ネットを捨てよ 草に触ろう)
●インターネット黎明期を経て…
「H-T-T-P、コロン…ってどれ? この縦に点々のやつ? で、えーと、スラッシュスラッシュ…」と、謎の呪文のようなURLをおぼつかない指先で初めて入力したのは1998年のこと。それから数年後、高校生になる頃には勉強も睡眠もそっちのけで、深夜に親が寝たのを見計らってから(ピーヒョロロロ〜という接続音がバレないようにモデムに毛布をかぶせて)チャットルームや掲示板に入り浸っていました。顔も素性も知らない“仲間たち”と毎夜のように語り明かした10代の日々、世界の誰とでもつながれる新時代の可能性に胸を踊らせていたものです。
あれから30年近くが過ぎ、今ではネットに対して背徳感やワクワクよりも義務感や焦燥感の方を強く感じる日々。そんな私が心掛けているいくつかのことは、朝起きて最初の30分はスマホを見ないようにする。思いついたことをすぐにポストせず、誤解を招いたり対立を煽ったりするような表現でないかじっくり検討する。わざわざそれをSNSで発信することにメリットはあるのかを考える。なんとなくスマホをいじりたくなったら代わりに本を10ページ読んでみる、など。いつも守れているわけではないですが、ネットの闇に飲み込まれずにいるための心得として意識しています。
身体の一部のようになったスマホを絶え間なくいじり続ける現代病に警鐘を鳴らす言葉が英語圏では次々と生まれています。例えば、何時間もあてもなく無意識にスマホをいじり続ける行為をゾンビに喩えた zombiescrolling。暴飲暴食などを表す binge から、集中的に大量のコンテンツを吸収することを bingescrolling。そして、世の中で起きている悲惨な事件や虐殺、戦争、気候危機、SNSの炎上騒動など、悲惨なニュースで絶望的な気分(a sense of doom)に陥るとわかっているのにスマホを見続けてしまう doomscrolling。本当に、どれも身に覚えがある行為で耳が痛いです…。
一日中娯楽コンテンツを消費し続けて brainrot(脳腐れ)しないように、何の目的でどれぐらいの時間をかけるのか意識してスマホを使う mindful scrolling を呼びかける専門家も増えています。
●ネットから“意識的”に離れる
SNSでは共通の関心がきっかけで仲良くなる人もいれば、あまり関わりたくない online troll もいます。トロールとは、北欧のおとぎ話などで悪さをする魔物や妖精のこと。気に入らない相手を誹謗中傷したり、デマを拡散したり、粘着的にちょっかいを出したりして、トラブルを起こす目的でネットを徘徊することを trolling といいます。トロールに捕まってしまったら、または自分自身がトロールになってしまったら、冷静な心を取り戻すために思い切ってスマホを窓から放り投げ…なくとも、しばらく距離を置くのがベスト。
そんな時は “Go touch grass”。最近、英語圏のネットでよく見かけるフレーズです。 「あんた、家にこもってネットばかりやってないでちょっと外の空気でも吸ってきたら?」というニュアンスの命令形として使われることも少なくないのですが、自戒を込めてSNS依存への注意を呼びかける文脈でも使われます。しばらく庭の草むしりに没頭したり、公園の芝生や川べりに寝っ転がったりするのも最高のデジタルデトックス。
TikTokで #touchgrass と検索すると、ネットから離れるために芝生や草原の草に触れる人々の姿が多数確認できます。(その様子をわざわざ撮影してネットにアップしているところがなんとも皮肉なのですが…)
今年3月には「Touch Grass」というアプリまで登場。TikTokやインスタグラムなど時間を無限に使ってしまいがちな SNSアプリと制限時間を設定すると、草に触っている自分の手元を写真に撮るまでロックを解除できないというシステムです。20代のデベロッパーが自身の doomscrolling の悩みを解消するために開発したアプリで、すでに10万回近くダウンロードされています。なお、室内の観葉植物や植え込みの茂みなどで代用しようとするとAI判定で却下されるそうです。厳しい! でも土の香りを嗅ぎながら芝生に寝転がる快感はネットを酷使して疲れた心も身体も癒してくれそうですよね。日本発祥の「森林浴」が forest bathing と英訳されて世界に広まったように、「デジタル空間から離れて草に触れよう」という考え方も果たして日本に浸透するでしょうか?
スクリーンから離れたくても、仕事の連絡がきたらすぐに返さなきゃいけないという現実もありますが、業務時間外の電話やメールなどに対応しなくていい権利(the right to disconnect・つながらない権利)を法律に制定する動きがヨーロッパ諸国やフィリピン、カナダなどから広まっています。日本でも働き方改革の一環として取り上げてほしい施策ですね。
ところで、あなたは自分の家から一番近い『草に触れられる場所』をすぐに思い浮かべられますか? 思いつかなかったら、ちょっと今からスマホを置いて散歩に行ってみませんか?

通訳・翻訳家・ラジオパーソナリティ
1985年東京都生まれ。9歳から23歳までニュージーランドで暮らし、オークランド大学で社会学・ジェンダー学・映像学などを学ぶ。日本に帰国後、フリーの通訳・翻訳者として国内外の社会課題の啓発や対話の現場に携わる。TBSラジオ「アシタノカレッジ」、「荻上チキ・Session」、YouTubeチャンネル「ポリタスTV」などにレギュラー出演。著書に『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(Gakken)がある。