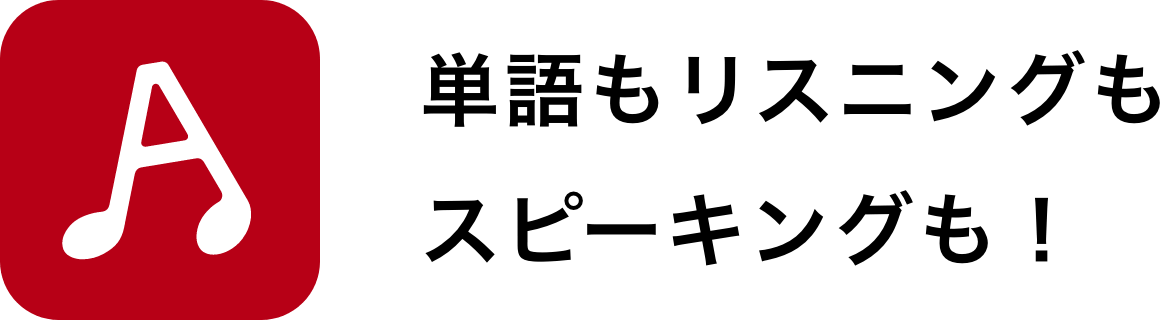生まれたばかりの英語たち #1 neurodiversity

時代とともに新しく生まれ、変化していく「言葉」。グローバル言語として使われる英語には、日本ではまだまだ認識されていない言葉があります。その誕生には、どんな社会的・文化的背景があるのでしょうか。キニマンス塚本ニキさんに「生まれたばかりの英語」について解説いただき、一緒に「新しい概念」について考えてみましょう!
neurodiversity(脳や神経の多様性)
●多様性とは
「今は多様性の時代だからね」
いつからか、他愛のない会話の端々でこういう言葉を聞くようになりました。多様性の時代。響きはいいけれど、個人的にはなんだか曖昧な表現でしっくりこないのが正直なところです。
当たり前のことですが、この世にひとりとして同じ人間はいない時点で、すでに「多様性」は普遍的な事象として成立しているはず。しかしこれまで何世代にもわたって教育や社会のさまざまな場面で画一性や均一性が求められてきた日本では、「普通」や「常識」などと言われる規範から外れた存在は白い目で見られがちです。
互いに気を遣い合う文化だからこそ組織的な管理が行き届きやすくなり、社会の規律が守られるという大きなメリットをもたらしますが、その裏で「みんなと同じでいなければならない」という同調圧力に悩まされてきた人も少数ではないはず。「突然、多様な人々が現れた」から多様性の時代と言われているのではなく、「みんなと同じフリをするのをやめた人たちが増えた」というふうに解釈するのが正確なんじゃないでしょうか。
●生まれ持った脳の特性を理解する
行政や企業が提唱するダイバーシティ推進の文脈でよく語られるのは、ジェンダー・性別やセクシュアリティ、人種やルーツなどですが、最近はこの他にも neurodiversity(ニューロダイバーシティ・脳や神経の多様性)という言葉も取り上げられるようになりました。これは脳や神経に由来するさまざまな特性の違いに優劣つけることなく、相互に尊重しようという考えから生まれた言葉です。
元々は90年代後半にASD(Autism Spectrum Disorder:自閉スペクトラム症)の当事者や支援者のオンラインコミュニティから広まった言葉ですが、現在はあらゆる非定型発達の症状、たとえばADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder:注意欠如多動症)やトゥレット症候群、知的障害、吃音、ディスレクシア(失読症)などのLD(Learning Disabilities:学習障害)から統合失調症、双極性障害、強迫性障害などの精神疾患も幅広く包括する一般用語として使われるようになっています。
10人いれば10通りの脳や神経システムがあるわけですが、一般的にマジョリティ側とされる neurotypical(定型発達)な人にとって「できて当たり前」なことが、neurodivergent(非定型発達)な人には無理難題のようになることがあります(理路整然と話す、複雑な文章を読解する、時間を守る、空気を読んで行動する、相手の気持ちに配慮した言葉を選ぶ、皮肉や冗談を間に受けない、など)。
世間的に「これぐらいできて当たり前」とされることがうまくできない悩みを抱える人たちが発達障害や学習障害などの診断を受けるケースが世界中で急増しているようです。これは決して優劣のレッテルを貼り付けることではなく、その人が生まれ持った特性を理解し、うまく活かす方法を模索するための重要なステップとも言えるでしょう。
同調圧力が強い環境を生き延びるために「なるべく普通でいること」は生存戦略になります。非定型発達の当事者が周囲から浮いた存在として見られないように、自分の言動を抑え込んだりして隠そうとすることを仮面になぞらえて masking と言います。
●いろいろな言葉があるけれど…
日本語の「障害(障がい・障碍)」という言葉の使い方をめぐってさまざまな意見があるように、英語圏でも disability や disorder などに関連する言葉は数十年前から何度も変容しています。例えば「障害者」を意味する言葉だと handicapped(ハンディキャップ)、person with special needs(特別なニーズがある人)、differently abled(異なる能力がある)など、これまでにいくつもの表現が生まれては消えていきました。時代の流れでケアの倫理観や世間の価値観が変化するとともに、一般的に適切とされる言葉も変わっているのです。その背景には「障害」を個人の能力不足や異常・欠陥としてみなす従来の「医学モデル」ではなく、当事者が排除され、不利益をこうむるような社会のあり方を問う「社会モデル」への移行があります。
私たちの言葉も意識も時代とともに変化するものです。学術的な研究だけでなく、SNSなどネットコミュニティからも言葉のレパートリーが増えています。neurodiversity については、社会的包摂を示唆する neuro-inclusive、障害を欠陥ではなく特性として肯定する neuro-affirming、さらには凸凹な個性をスパイスのように味わい深いものとして表現する neurospicy なんて遊び心のある言葉もレパートリーに加わっています。「なにが適切な言葉か」という議論は今後も定期的に起こるでしょうが、どんな言葉が使われようとも一番大事なのは、特定の能力を持ち合わせる人以外を排除するような ableism(能力主義)に陥らないことです。
でも本当に、そこまで難しく考えなくてもいいと思うんです。一見、同質的に見えても、ひとりひとりの脳・神経の働き方が違うことを知り、自分とは違う人間を否定せずに「世の中いろんな人がいるなあ」とゆるく受け入れるだけでも、多様な人がもっと生きやすい社会を作れるんじゃないんでしょうか。

通訳・翻訳家・ラジオパーソナリティ
1985年東京都生まれ。9歳から23歳までニュージーランドで暮らし、オークランド大学で社会学・ジェンダー学・映像学などを学ぶ。日本に帰国後、フリーの通訳・翻訳者として国内外の社会課題の啓発や対話の現場に携わる。TBSラジオ「アシタノカレッジ」、「荻上チキ・Session」、YouTubeチャンネル「ポリタスTV」などにレギュラー出演。著書に『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(Gakken)がある。